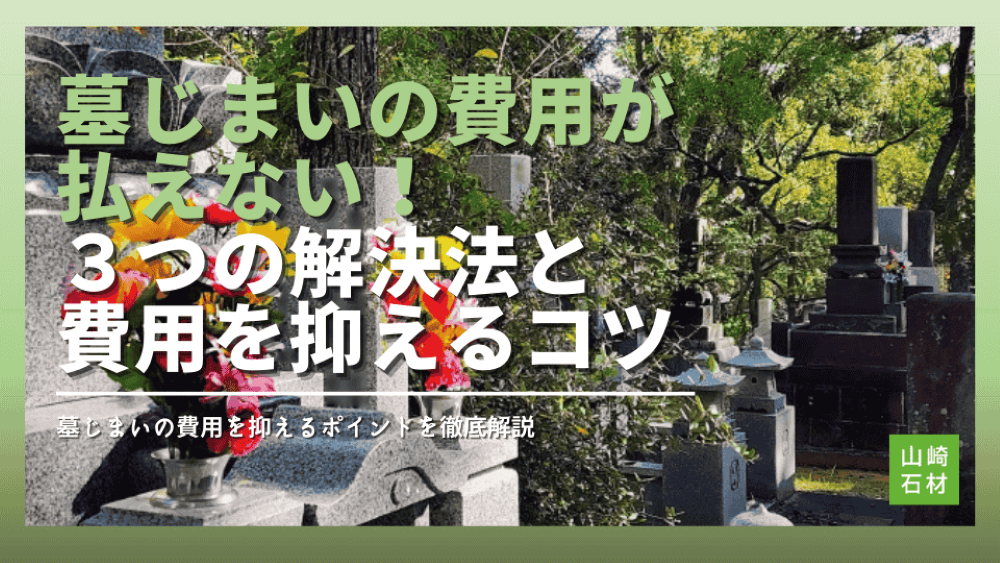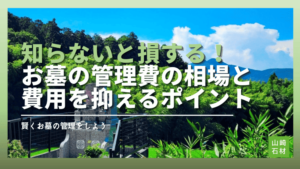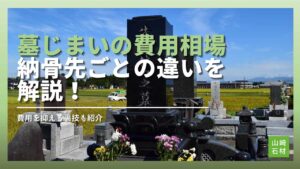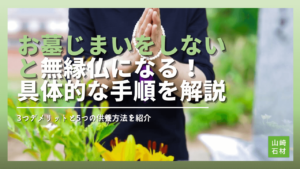女性
女性墓じまいをしたいけど、費用が高すぎて払えない…。
ご家族の状況などで、墓じまいを検討したいけれど、費用が捻出できず悩む人は少なくありません。
経済面の不安が拭えずに、墓じまいを進められず困っているという方も多いでしょう。
しかし、墓じまいの費用は、適切な手段を選ぶことで負担を大幅に減らせます。
そこで本記事では墓じまいの費用を支払えないときの解決策や、費用を抑えるコツを解説しています。
- 墓じまいの費用が払えないときの解決法
- 墓じまいの費用を抑えるコツ
- 墓じまいの費用相場
さらに、墓じまいの費用について多くの方が疑問を抱くポイントの対処法も紹介しますので、ぜひご覧ください。



本記事を読むことで、経済的な負担を軽減しながら墓じまいをする方法が分かりますよ!
墓じまいの費用が払えないときの解決法3つ


墓じまいの費用が払えず悩んでいる方も、適切な解決策を取ることで負担を軽減できます。
- 家族・親族に相談して費用を負担してもらう
- メモリアルローンを利用する
- 自治体の補助金を活用する
詳しくみていきましょう。
1.家族・親族に相談して費用を負担してもらう
墓じまいの費用が高額で支払いが難しい場合、家族や親族に相談しましょう。
お墓の継承者だからといって、墓じまいの費用を全て1人で負担する必要はありません。
まずは家族や親族に相談し、墓じまいの必要性を丁寧に説明した上で、費用の分担について協力をお願いしましょう。
その際、相談は墓じまい直前ではなく、十分な時間を確保し余裕を持って行うことが大切です。
お墓を共同で使用してきた場合や今後も関係者が供養を続ける場合には、責任や負担を分け合うことは自然な流れです。
親族同士で協力することで、経済的な負担を減らしながらスムーズに墓じまいを進められます。
2.メモリアルローンを利用する
メモリアルローンとは、墓じまいや改葬に必要な費用を分割払いで支払える専用のローン商品で、多くの金融機関や霊園関連の会社が提供しています。
メモリアルローンの特徴は、金利が平均5%前後とフリーローンやカードローンの金利(平均15%前後)と比べて低いことです。
また、メモリアルローンは当日に審査の結果が出ることも多く、すぐに利用しやすい点が魅力と言えます。
ただし、ローンを組む際には手数料が発生するため、事前に総返済額を確認し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
さらに、ローンを提供する会社の信頼性や条件を比較検討することで、より安心して利用できる選択肢を見つけることができます。
3.自治体の補助金を活用する
墓じまいにかかる費用の一部を、自治体が助成してくれる場合があります。
ただし、助成金を申請できる自治体をまとめた専用のWebサイトは現在ありません。
そのため、お墓がある地域の市役所に直接問い合わせて確認する必要があります。
助成金の上限金額は自治体によって異なりますが、活用することで費用負担を大幅に軽減できる可能性があります。
助成金を申請できる条件に該当する場合は、積極的に申請を検討しましょう。
ただし、助成金が支給されるのは、墓石の解体工事が完了した後のため、工事費用は一時的に自身で準備する必要があります。
手持ち資金が不足している場合は、事前に資金調達を計画することが大切です。
墓じまいの費用が払えない!費用を抑えるコツ3つ


墓じまいの費用は、工夫次第で大幅に負担を軽減できます。具体的な方法には、以下の3つがあります。
- なるべく費用のかからない納骨先を選ぶ
- 石材店の相見積もりをとる
- 両家墓にする
詳しくみていきましょう。
1.なるべく費用のかからない納骨先を選ぶ
新しい納骨先にかかる費用を抑えることで、墓じまいの費用負担を軽減できます。
お墓は、墓地管理者や霊園から借りた土地に建てられており、墓石は購入者の所有物です。土地の使用料や地代は、管理費として必要です。
例えば、広いスペースがいらない樹木葬や納骨堂は、一般的な墓地に比べて管理費用を抑えられます。
樹木葬は、墓石の代わりに樹木を墓標として利用する供養方法で、費用相場は30万円〜150万円程度です。
一方、納骨堂は屋内に遺骨を保管する施設で、費用相場は30万円〜150万円程度です。
そして、自宅から近い場所の墓地を選べば、交通費や維持費を抑えられるでしょう。
納骨先によって墓じまいの費用相場は異なります。さらに詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひご参考ください。
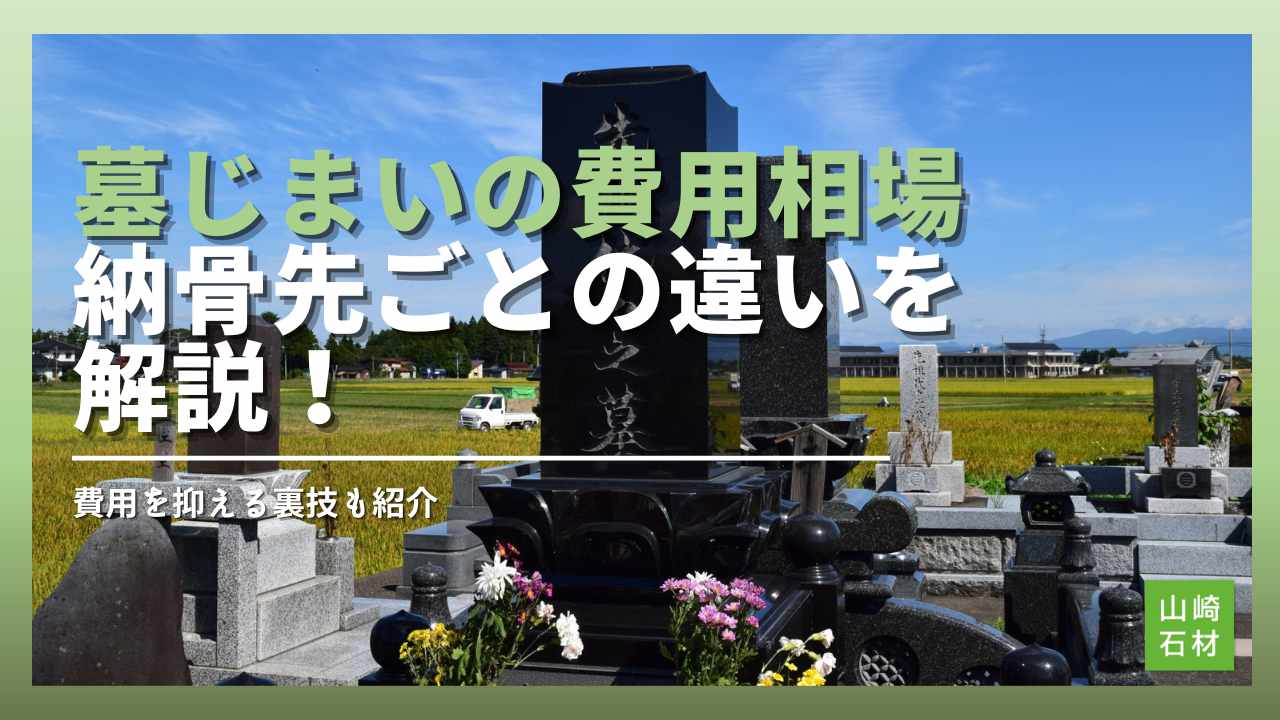
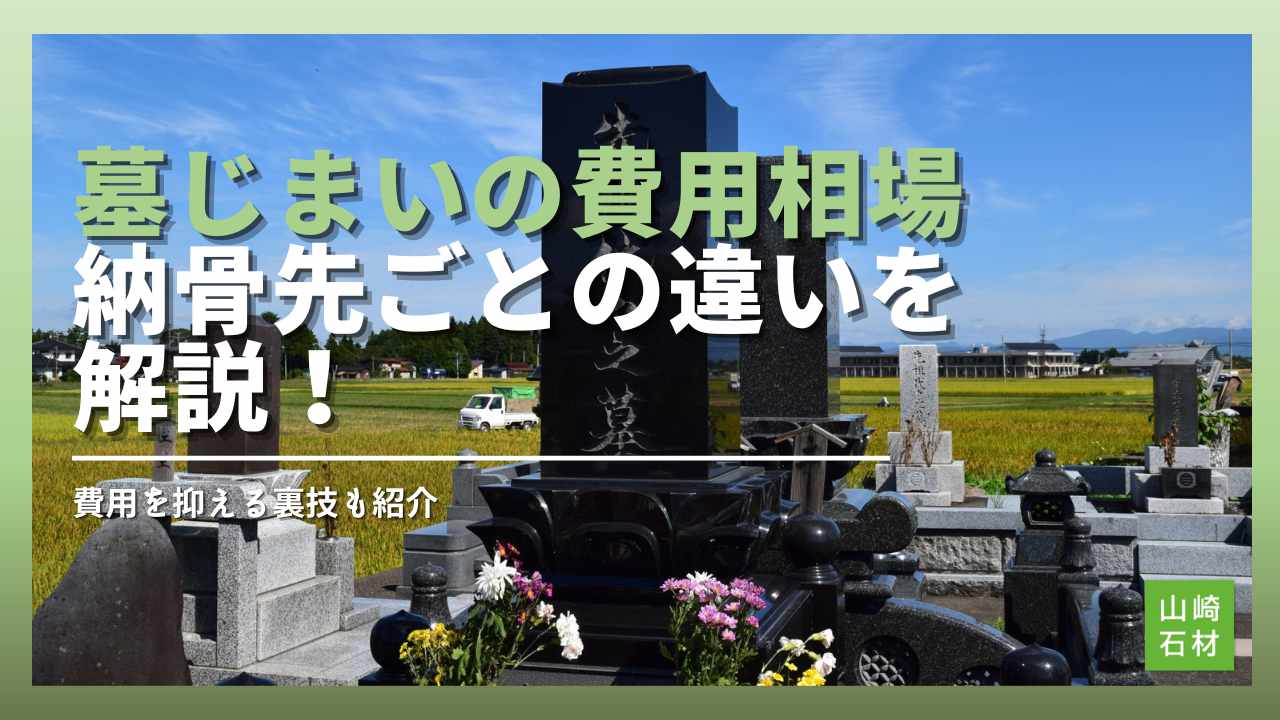
2.石材店の相見積もりをとる
墓じまいの費用を抑えるために、複数の石材店から相見積もりをとることは有効です。
石材店によって、墓石の撤去や処分にかかる費用、手続き代行サービスの有無などが異なるため、比較検討を行うことで最適な業者を選ぶことができます。
相見積もりをとる際は、単に価格だけでなく、見積もり内容やサービスの質も確認しましょう。
たとえば、費用に墓石の撤去後の整地作業や、改葬手続きのサポートが含まれているかなどがポイントになります。
また、業者の評判や口コミも事前に調べておくと安心です。
複数の業者を比較することで、余分な費用を削減できるだけでなく、信頼できる業者に依頼できます。
効率的に墓じまいを進めるためにも、相見積もりは欠かせないステップです。
3.両家墓にする
両家墓とは、複数の家族のお墓を1つにまとめて管理する形のお墓のことです。
現在所有しているお墓を撤去し、親戚や他の家族のお墓に遺骨を埋葬するため、新たなお墓を建てる必要がなく、費用負担を少なくできます。
複数のお墓を1つにまとめることで管理やお墓参りの手間が減り、承継者がいない場合の問題を解消できるといった利点があります。
ただし、親族間でしっかり合意を得ることや、墓石や墓誌に記載する名前について事前に相談しておくことが重要です。
これにより、後々のトラブルを防ぐことができます。
また、墓地や霊園によっては両家墓を認めていない場合や、宗派によっては改宗が必要になるケースもあります。
そのため、事前に墓地や寺院に確認を取り、規約や条件を把握しておきましょう。
両家墓について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご参考ください。


墓じまいにかかる費用の平均は約40万〜150万円


墓じまいの費用は、お墓の大きさや場所、改葬先の条件によって異なりますが、一般的にはおおよそ40万円から150万円が相場とされています。
費用に幅がある理由は、墓じまいに伴うお布施や離檀料、新しい納骨先の費用などが状況によって異なるためです。
墓じまいを行う際、現在のお墓に関連して発生する費用は、以下の5つ挙げられます。
| 墓じまいにかかる項目 | 費用 |
|---|---|
| 墓石の撤去費用 | 約10万円/平方メートル |
| 閉眼供養 | 約3万~5万円 |
| 寺院への心遣い | 約3万円~20万円 |
| 納骨先にかかる費用 | 約5万円~150万円 |
| 開眼供養 | 約3万円~30万円 |
墓じまいの費用に関してよくある質問


墓じまいの費用を考えたときに、さまざまな疑問が出てくることもあるでしょう。
ここでは、墓じまいの費用負担に関してよくある質問に回答していきます。
- 墓じまいの費用は誰が払うものですか
- 墓じまいをすると不幸になるというのは本当ですか
- 墓じまいをすると後悔することはありますか
- 墓じまいをしないとどうなりますか
詳しく解説していきます。
1.墓じまいの費用は誰が払うものですか
墓じまいの費用は、一般的にはお墓の承継者が負担します。
承継者とは、家族内でお墓を引き継ぐ人を指し、配偶者や子ども、孫などが該当します。
承継者がいない場合や、費用負担が難しい場合は親族で相談し、費用を分担するのも1つの方法です。
墓じまいに関する費用負担に法的な決まりはありませんが、親族間で十分な話し合いを行い、負担方法や金額を明確にしておくことが重要です。
特に、墓じまいに伴う離檀料や改葬費用などは高額になるケースもあるため、計画的に準備を進める必要があります。
親族と協力することで経済的な負担を軽減し、スムーズな墓じまいを実現することが可能です。
2.墓じまいをすると不幸になるというのは本当ですか
「墓じまいをすると不幸になるのでは?」と心配する人もいますが、仏教の教えでは故人が祟るという考え方はありません。
墓じまいそのものが不幸を招くといった根拠はないため、必要以上に不安を抱える必要はありません。
墓じまいという言葉には、「お墓をしまう」「使わなくなったお墓を片付ける」という印象があり、それが「ご先祖様をないがしろにする」というイメージにつながりやすいのかもしれません。
しかし、実際の墓じまいはお墓の管理が難しくなった状況を改善し、供養しやすい形に変えるための行為です。
たとえば、永代供養墓に遺骨を移すことで、自分が管理できなくなった後も寺院や霊園が供養を続けてくれます。
墓じまいはご先祖様を大切に思い、将来にわたって供養を続ける方法の1つと言えるでしょう。
改めて家族が集まりやすい場を作る意味でも、お墓の改葬は重要です。



本家が子孫がおらず、お墓の継承者がいない場合、分家がお墓を継承することも可能です。
3.墓じまいをすると後悔することはありますか
墓じまいをしたあと、手を合わせて故人を偲ぶ場所がなくなったことを後悔するケースがあります。
お墓は、故人や先祖を身近に感じ、心の拠り所となる大切な場所です。そのため、撤去した後に「やっぱり残しておけばよかった」と感じる人も少なくありません。
特に、墓じまいを急いで決断した場合や、親族間で十分な話し合いができていなかった場合に後悔が生じることが多いです。
そのため、墓じまいを進める際には、家族や親族全員が納得し、合意を得ることが重要です。
また、遺骨をどのように供養するのか、供養先がしっかりとした場所であるかなども慎重に検討しましょう。
墓じまいは大きな決断のため、焦らず十分に準備をしてから進めることで後悔を防ぐことができます。
4.墓じまいをしないとどうなりますか
お墓の後継者がいない場合、無縁仏として取り扱われる可能性があります。
供養が途絶えることを心配して墓じまいを検討する人もいますが、費用がかかるイメージから諦めるケースも少なくありません。
しかし費用を抑えた墓じまいを選ぶことで、経済的な負担を軽減しながら先祖供養を続けることが可能です。
また、お墓の管理費を長期間支払わないと、霊園側でお墓が撤去され、遺骨が合祀墓や無縁仏の施設に移されることがあります。
この場合遺骨を取り出すことは難しく、供養が行われない場合もあるため、後悔することもあるでしょう。
こうした事態を避け、大切なご先祖様の供養をするためには、早めに墓じまいを検討し、適切な供養の形を整えることが重要です。
まとめ


本記事では墓じまいの費用相場や、払えない時の解決方法などを解説していきました。
以下、墓じまいの費用が払えないときの解決法です。
- 家族・親族に相談して費用を負担してもらう
- メモリアルローンを利用する
- 自治体の補助金を活用する
墓じまいの費用を抑えるコツは以下の3つです。
- なるべく費用のかからない納骨先を選ぶ
- 石材店の相見積もりをとる
- 両家墓にする
また、墓じまいの費用はお墓の大きさや立地、改葬先によって異なり一般的な相場は40万円〜150万円程度です。
費用は主に承継者が負担しますが、継承者がいない場合は親族間で話し合う必要があります。
墓じまいは供養しやすい形に変えるための行為であり、不幸を招くと懸念する必要はありません。
しかし、故人を偲ぶ場所がなくなったり、親族間の話し合いが不足すると後悔する場合があるので注意が必要です。
一方で、墓じまいをしない場合は無縁仏として扱われ、供養が途絶えるリスクがあります。
適切なタイミングで計画的に進めていきましょう。