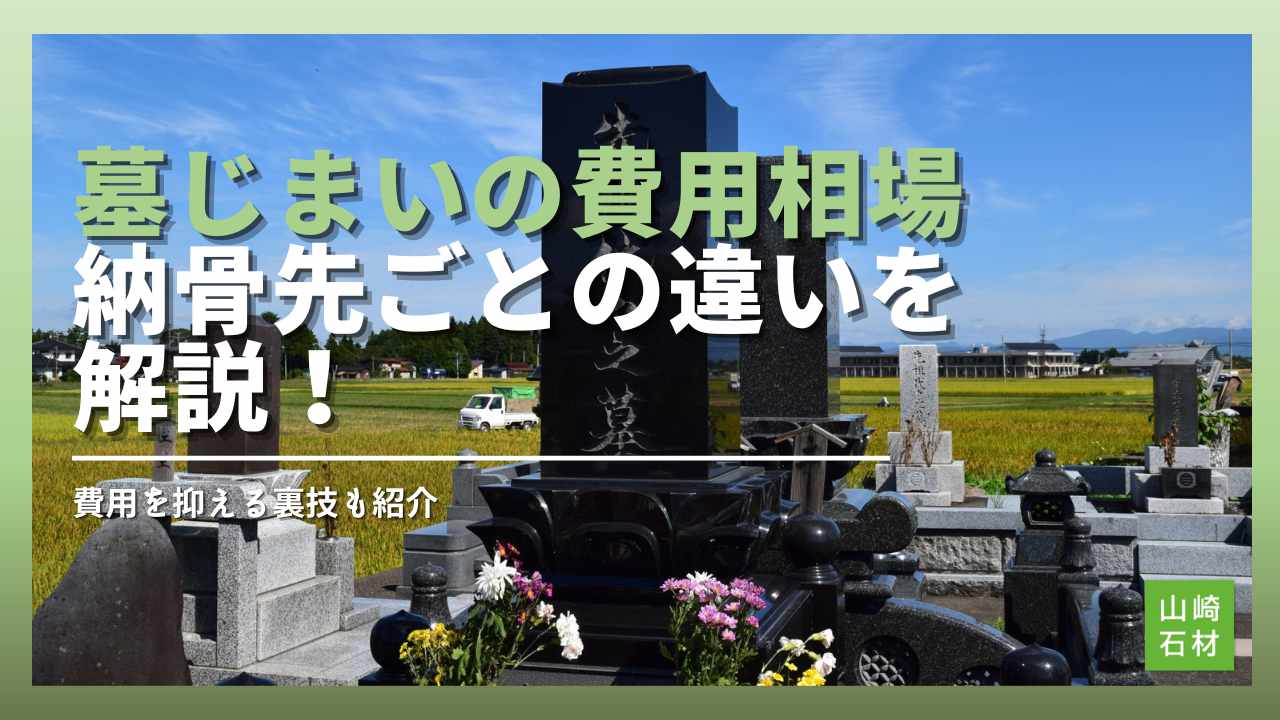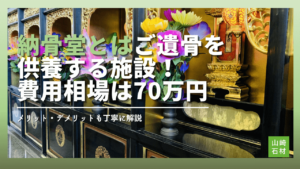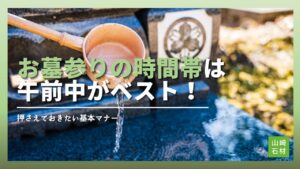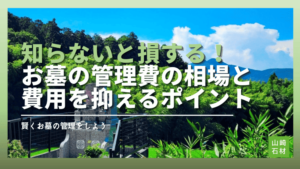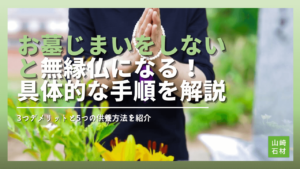女性
女性墓じまいを考えたいけど、どれぐらいの費用がかかるのかわからなくて不安…
お墓参りを続けてはいるものの、さまざまな事情があり墓じまいを検討している人もいることでしょう。
墓じまいは、供養の仕方やお墓の種類によって費用が変わるため、事前に知っておくことが大切です。
そこでこの記事では、墓じまいにかかる費用の相場や、納骨先ごとの費用の違いを詳しく解説します。
- 墓じまいにかかる費用相場
- 墓じまいの費用を抑える方法
- 墓じまいの費用に関してよくある質問



この記事を読めば、ご自身やご家族にあった方法で墓じまいができるようになるため、ぜひご覧ください。


石一筋135年の石材店が次世代に思いを継ぐ墓づくりを提案
創業135年(2023年現在)、北海道を代表する石材店として滝川市で歴史を刻み「お墓は人生の物語」をテーマに墓石デザインプロデューサーとして、大切な人の想いを未来の家族に届けるお墓づくりを目指します。
墓じまいの費用相場は約40万円〜150万円


墓じまいの費用は、お墓の大きさや立地、改葬先によって異なりますが、一般的には40万円から150万円が相場です。
墓じまいとは、墓石を撤去して、更地にして墓地の管理者に返却することを指します。
お墓を継ぐ人がいない、遠方に住んでいて、お墓参りをするのが難しいなどさまざまな事情により、墓じまいを考える人は少なくありません。
お墓を撤去したとしても、お墓に納められている遺骨は他の方法で供養し、弔う必要があります。
費用に幅があるのは、墓じまいにかかるお布施や離檀料、納骨先によってかかる金額が変わるためです。
次の、項からは、墓じまいにかかる費用相場とともにどのような費用なのかを詳しく解説します。
墓じまいにかかる5つの費用


墓じまいをするときには、現在のお墓にまつわる費用として、以下の5つがあります。
- 墓石の撤去費用
- 閉眼供養 (へいげんくよう)
- 寺院への心遣い
- 納骨先にかかる費用
- 開眼供養(かいげんくよう)
それぞれ、詳しく解説します。
1.墓石の撤去費用
墓石の撤去の費用相場と、手続きにかかる費用相場は、下記の通りです。
- 費用相場:約10万円/平方メートル
- 改葬許可証に500円程度
今あるお墓の撤去費用は、1平方メートルあたり約10万円が目安です。
墓石の大きさや撤去方法によって変わります。 撤去作業は、石材店に見積もりを依頼します。
お寺や霊園によっては、業者が指定されている場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
撤去費用には、更地にする作業や石の処分費用も含まれているのが一般的です。
また、墓じまいをするときには、「改葬許可証」の手続きにも費用がかかります。
自治体によって発行手数料は異なりますが、相場は500円です。
2.閉眼供養(へいげんくよう)
お墓を撤去するときにかかる、閉眼供養の費用相場は、以下の通りです。
お布施の金額は寺院ごとに異なりますが、一般的には3万円から5万円が相場です。
閉眼供養(へいげんくよう・へいがんくよう)とは、お墓から遺骨を取り出すための儀式です。
僧侶が読経をし、「お墓に宿っていた故人の魂を解放する」ために行います。
3.寺院への心遣い
お墓じまいとともに離壇をする場合は、「これまでお世話になりました」と、寺院に心遣いをお支払いします。
心遣いの相場は3万円から20万円程度で、およそ法要1回分と捉えておきましょう。
寺院墓地の場合は、お墓を撤去して寺院に返すことは、離檀を意味します。
しかし、自治体の墓地墓園の場合は、お墓じまいをしても離檀になるとは限らないため、離檀料ではなく心遣いとしてお渡ししましょう。
トラブルを避けるためにも、事前に石材店などに相談し、アドバイスをもらうのもおすすめです。



北海道のように自治体の墓地墓園が多い地域は、お墓じまいをしたからといって離檀になるわけではないため、心遣いとして渡すのがよいでしょう。
4.納骨先にかかる費用


墓じまいをしたあとの納骨先は、納骨方法によって費用が大きく異なります。 ここでは、以下7つの選択肢ごとの相場と方法について解説します。
- 一般的なお墓
- 樹木葬
- 納骨堂
- 永代供養墓
- 散骨
- 先祖代々のお墓に合葬
- リノベーションして一族墓や両家墓に改装
1つずつ、みていきましょう。
1.一般的なお墓


墓石を設置し、下に遺骨を納める形式の一般的なタイプのお墓で、費用相場は50万~150万円です。
霊園や寺院にお墓を建て、家族や近親者が継承していく形式のお墓です。
一度建てれば代々同じお墓を使えるため、先祖代々のつながりを感じられるという特徴があります。
大人数を納めることができ、代が下っても先祖の歴史を伝えられるため、家族の絆を長く感じられるお墓のスタイルでもあります。
霊園や寺院に、年間の管理費を支払う必要があります。
2.樹木葬
樹木葬とは、遺骨を埋葬して、墓石を建てずに樹木や花をシンボルとする形式のお墓で、費用相場は30万~150万円程度です。
個人用や家族用など、用途によって費用は異なりますが、比較的低価格で済みます。
永代供養が基本で、継承者の負担が少ないのが特徴です。
しかし、一度埋葬すると遺骨を取り出すことができないことがあると理解しておく必要があります。
樹木葬について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
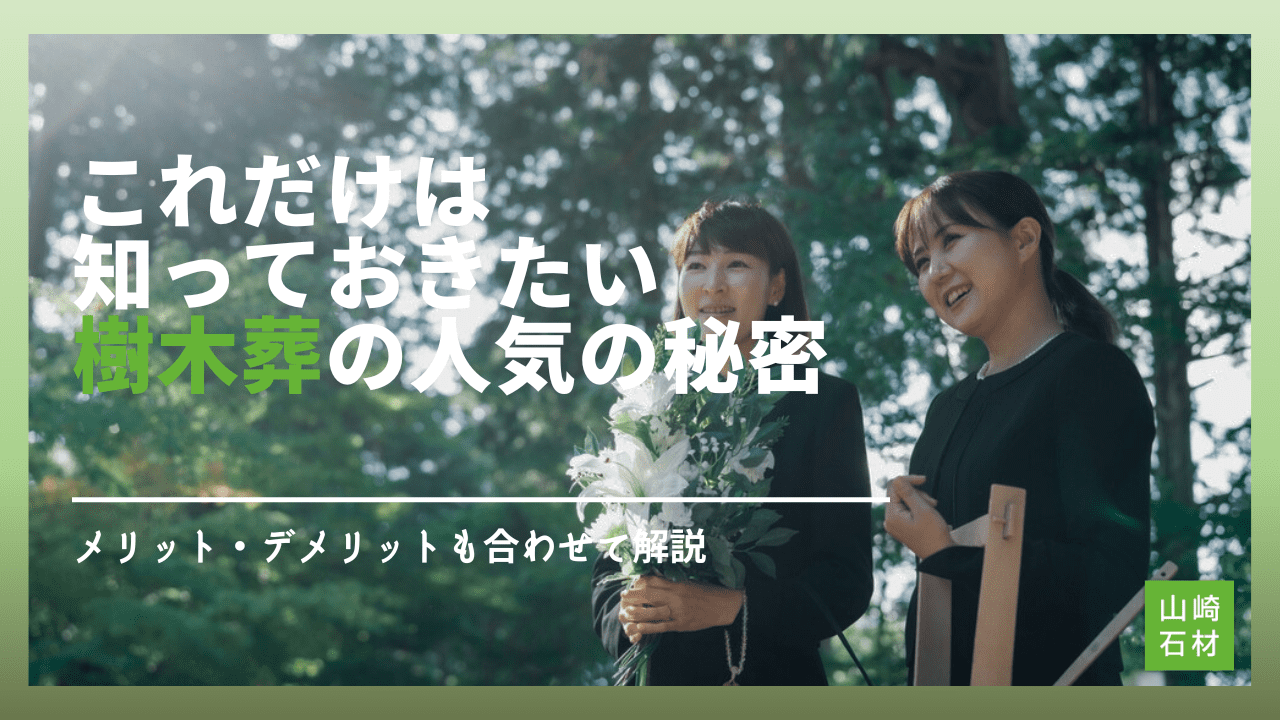
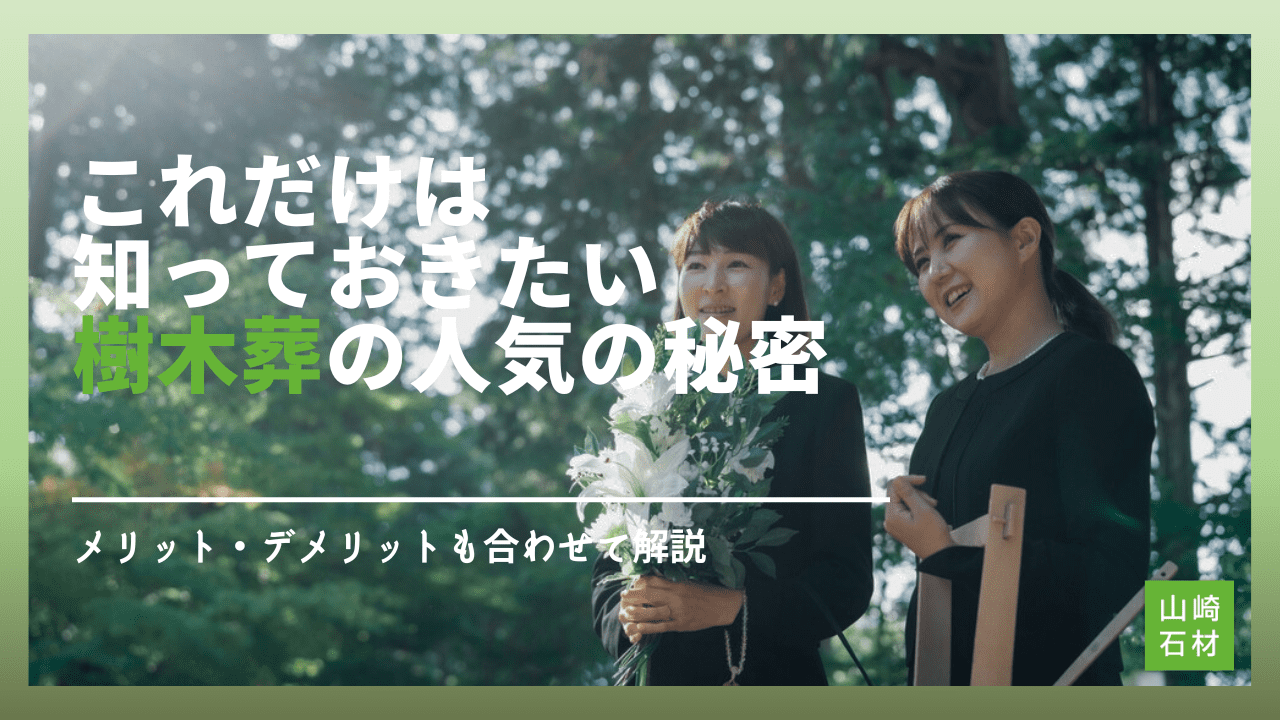
3.納骨堂
納骨堂とは、遺骨を安置する場所を備えた施設のことを指します。
施設の形式はさまざまで、費用相場は30万~150万円です。
一般的なお墓と同様に年間の管理費がかかりますが、交通アクセスが良い場所にあるという特徴があります。
天候に左右されず、快適にお参りできるのも魅力です。
4.永代供養墓


永代供養墓とは、遺族に代わって寺院や霊園が故人の供養を永続的に行うお墓のことです。
一般的なお墓は、親族が定期的にお参りや管理を行う必要がありますが、永代供養墓では、その負担が軽減され、供養や管理が長期にわたって継続されます。
特に、後継者がいない場合や、お墓の管理をする人が少ない場合に選ばれることが多いです。
永代供養墓は、個別のお墓だけでなく、合同墓として他の遺骨と一緒に納められる場合もあります。
費用相場は5万~150万円程度と、幅があります。多くの場合、一度支払えば追加の費用はかかりません。
ただし、寺院や霊園によってルールは異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
永代供養の費用相場や注意点について、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。


5.散骨


散骨とは、火葬後の遺骨を粉状にし、海や山、森林などに遺骨をまく方法です。
費用相場は散骨の仕方によって異なり、5万~70万円程度と幅があります。
お墓の管理が難しい場合や、「自然に還りたい」と考える人に選ばれることが多い供養の形です。
日本で散骨をするには法律上の手続きは必要ありません。
しかし、自治体によっては禁止されていることもあるため、遺骨を撒く場所に関しては配慮が必要です。
海への散骨の他にも、山岳散骨や宇宙散骨などの方法があり、散骨する場所や方法には一定のマナーや規制があるため、事前に確認しておきましょう。
散骨にかかる費用や具体的な方法については、以下の記事をご覧ください。
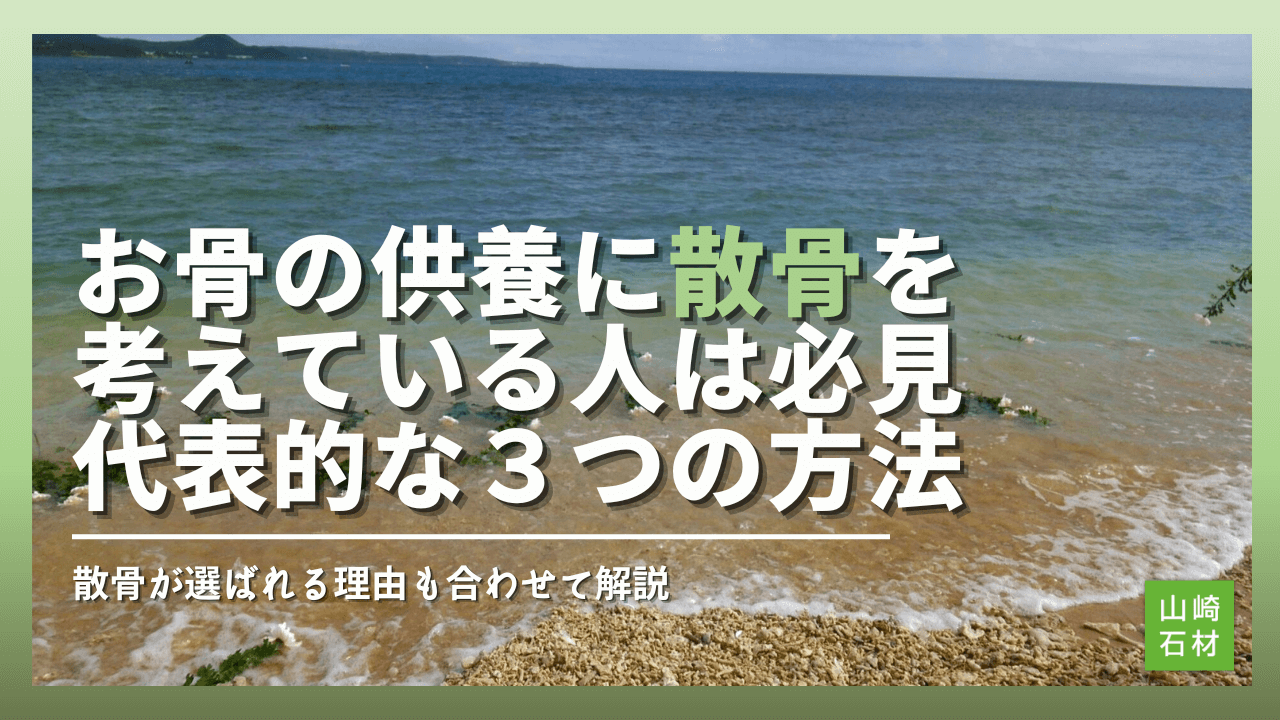
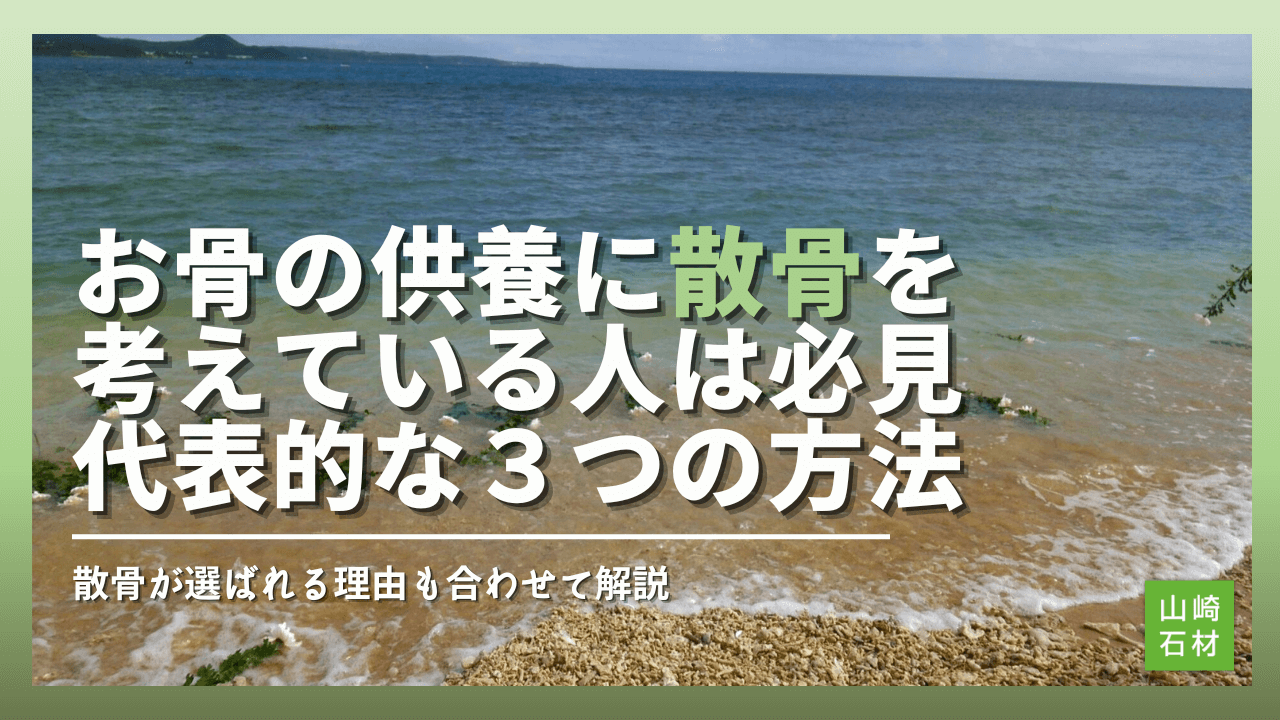
6.先祖代々のお墓に合葬
墓じまい後の納骨先としては、先祖代々のお墓に合葬するという方法もあります。
これまで別々のお墓にあったご遺骨を、1つのお墓にまとめて納めることです。
すでにあるお墓に合葬する場合には、新しくお墓を建てる費用はかかりません。
合葬するとお墓参りが1ヶ所で済み、お墓にかかる維持費も減らせます。
しかし、遺骨を安置するカロートに十分なスペースが必要です。合葬先のお墓のスペースを、事前に確認してから進めましょう。
7.リノベーションして一族墓や両家墓に改装
墓じまいをしたあとの納骨先の選択肢として、お墓をリノベーションし、一族墓や両家墓に改装する方法があります。
家族または同一の姓の親族の遺骨を1つのお墓に納骨することを「一族墓」、両家の墓を1ヶ所にまとめたお墓を「両家墓」と言います。
工事の内容によって異なりますが、リノベーションの費用相場は、40万~150万円です。
既存のお墓の本体が、価値のある石や思い入れのあるお墓の場合は、墓石を一度解体して、工場で磨き直しをしてきれいにすることも可能です。
ただし、お墓をまとめるときには親族から理解を得る必要があり、宗派が違うと建てられないこともあるため、注意が必要です。
5.開眼供養(かいげんくよう)


墓じまい後の納骨をするときには、開眼供養を行います。
開眼供養のお布施の金額は、寺院にもよりますが一般的に3万円から30万円程度が相場です。
ただし、宗派によっては開眼供養を必要としない場合や、散骨などの際には省略できることもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
お墓を開眼供養とは、新たにお墓を建てた際や樹木葬を行う際に、僧侶に読経してもらう儀式のことを指します。
故人の魂をお墓に宿す重要な儀式です。
墓じまいの費用を抑える方法3つ


墓じまいにかかる費用を抑える方法には、以下の3つがあります。
- お墓の撤去を依頼する業者を比較検討する
- 費用のかからない納骨先を選ぶ
- 補助金を利用する
それぞれについて、詳しく解説します。
1.お墓の撤去を依頼する業者を比較検討する
お墓の撤去を依頼する際は、複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討することが大切です。
業者によって撤去作業の料金が異なるため、同じ条件でも数十万円の差があることもあります。
適正価格を把握するためにも、2〜3社の石材店に見積もりを依頼しましょう。
また、業者を選ぶ際には、費用だけでなく、実績や評判も確認することも大切です。
口コミや紹介を参考にしつつ、信頼できる業者を見つけることが後々のトラブルを防ぐことにもつながります。
流れや必要な手続きについても事前に確認しておくと、スムーズに進められるでしょう。
2.費用のかからない納骨先を選ぶ
墓じまいの費用を抑えるには、費用のかからない納骨先を選ぶのもポイントです。
例えば、自治体管理の合併墓を選ぶといった選択肢があります。
しかし、自治体ごとに、その自治体の住民票や本籍があるなどの制限があるため、利用できるか事前に確認しておきましょう。
また、永代供養墓や樹木葬、散骨であれば、お墓を建てる費用や管理料はかかりません。
宗教や習慣にこだわらず、負担を減らしたい場合におすすめの方法です。
3.補助金を利用する
一部の自治体では、墓じまい(墓地返還)に関するサポートや推進活動を行っているケースがあります。
なお、民間の霊園や寺院の墓地は対象にならないことには注意が必要です。
自治体が提供している墓じまい支援の例としては、以下のような補助金があります。
- 公園墓地還付金
- 合葬墓特例使用許可制度
- 原状回復義務の免除制度
それぞれ、対象者や補助金の申請時期があります。
お住まいの自治体で補助金制度があるかは、ホームページを確認するか、窓口で確認しましょう。
墓じまいの費用に関してよくある質問


墓じまいをするときには、費用に関してさまざまな疑問が出てくるものです。
ここでは、墓じまいの費用に関してよくある質問に答えていきます。
費用は誰が払うものですか?
墓じまいの費用負担は、家族間でトラブルになることも少なくありません。
一般的には、祭祀継承者とするが費用を負担することが多いです。 祭祀継承者とは、葬儀や法事などを取り仕切る人のことです。
しかし墓じまいの費用は高額になることもあり、全てを一人で支払うのは難しいことも珍しくありません。
支払いのルールがあるわけではないため、家族や親族と話し合いをして、費用を負担する方法を検討するのが現実的と言えます。
お墓代の費用を誰が出すのか、トラブルを防ぐ方法などについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。


墓じまいの費用が払えない場合はどうすればいいですか?
墓じまいの費用が予想以上に高額で、大きな負担に感じる方もいるかもしれません。
費用が払えない場合は以下の3つの解決策があります。
家族や親族と話し合う
お墓じまいの費用がご自身だけで負担するのが難しい場合、親族に相談することをおすすめします。
お墓じまいは、ご家族にとって大きな決断です。事前に親族に相談し、それぞれの意見をしっかりと聞き合うことが大切です。
負担を分担することで、費用の問題も解決しやすくなりますので、まずは家族や親族に相談してみましょう。
自治体へ問い合わせる
住んでいる自治体によっては、墓じまいに関する補助金制度を設けている場合があります。
お墓がある地域の市役所窓口などで問い合わせてみましょう。
ただし、多くの場合、墓石の撤去工事が完了した後に助成金が支給されます。
そのため、工事費は一度自分で立て替える必要があることを理解しておきましょう。
メモリアルローンを利用する
お墓に関する費用をカバーするための「メモリアルローン」というローン制度も利用できます。
メモリアルローンは、お墓や葬儀など、故人を供養するための費用を借りられるローンです。
一般的なフリーローンと比べて、審査がスピーディーで通りやすく、金利も平均5%前後と低く設定されている点が特徴です。
お墓を建てる費用や、お墓をなくす「墓じまい」の費用など、さまざまな用途に使えます。
お墓じまいの費用がないときの解決策についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。


墓じまいをしないとどうなりますか?
お墓を管理する人がいなくなり、放置された状態のものを「無縁墓」や「無縁仏」と呼びます。
特に、山間部の墓地や共同墓地で管理されず放置されると、お墓は次第に荒廃してしまいます。
お寺や霊園で管理されているお墓が無縁墓となると、霊園の判断でお墓が撤去される場合もあります。
無縁仏のお墓になってしまうと管理者が費用を負担するため、供養されなくても文句は言えません。
永代供養と無縁仏は違うため、墓じまいをして供養する方法を検討することが大切です。
無縁仏になるリスクについて、もう少し詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
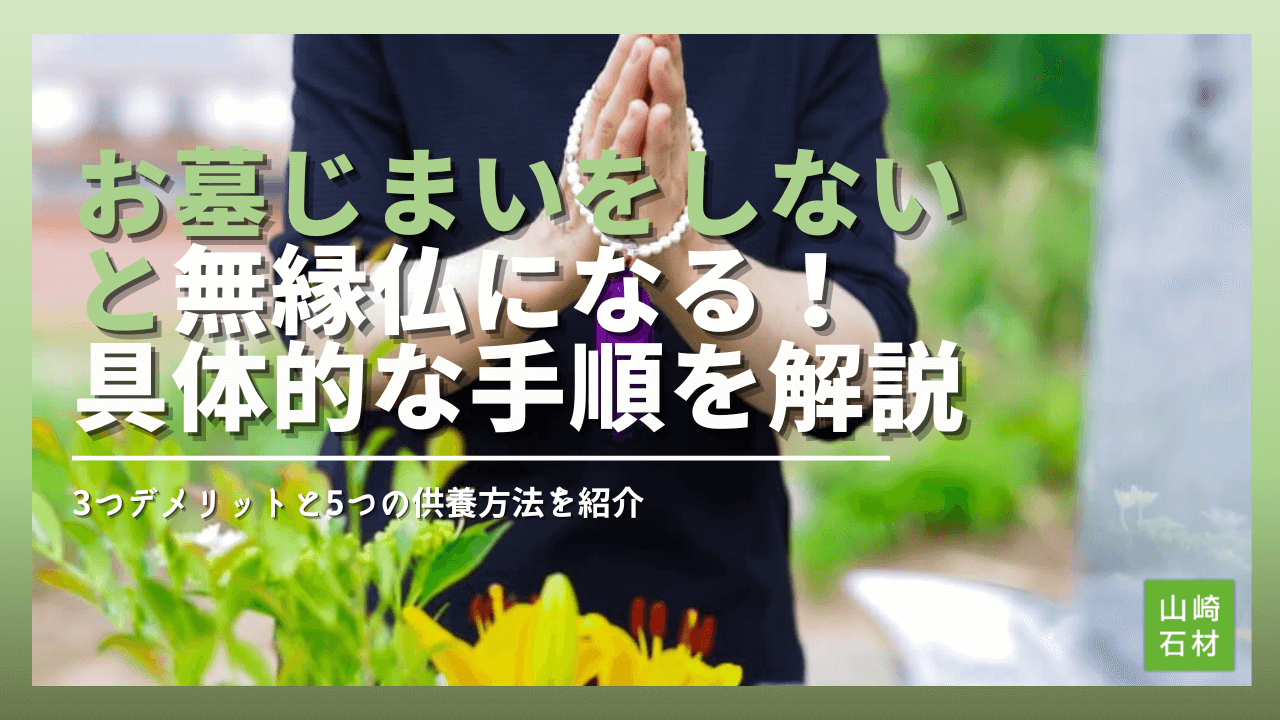
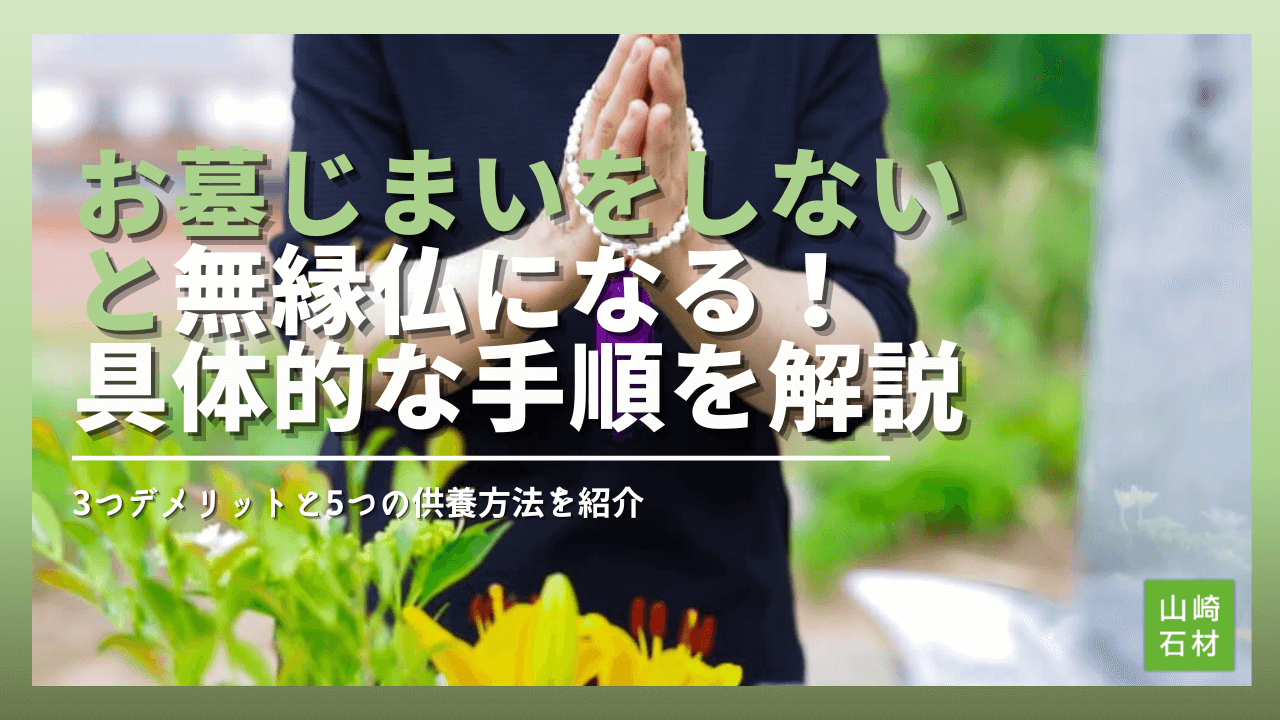
まとめ


今回は、墓じまいにかかる費用について、詳しく解説しました。
- 墓じまいの相場は50万~300万円程度
- 墓石撤去費用は10万円/平方メートルが目安
- 閉眼供養や離檀料は3万~20万円程度
墓じまいの費用を抑える方法は、以下があります。
- 複数の業者から見積もりをとる
- 永代供養墓や散骨など、安価な納骨先を選ぶ
- 自治体の補助金や支援制度を活用する
墓じまいにまつわるトラブルを防ぐには、以下の注意点に留意しましょう。
- 墓じまいの費用は祭祀継承者が多めに負担することが多い
- 費用が払えない場合は親族に協力してもらうかローンの利用を検討する
- 墓じまいをしないと無縁墓として管理者に撤去されることがある
山崎石材工業では、お墓代の見積もりを無料でお出しいたします。まずはお墓代の見積もりを出したいという方はお気軽にご相談ください。